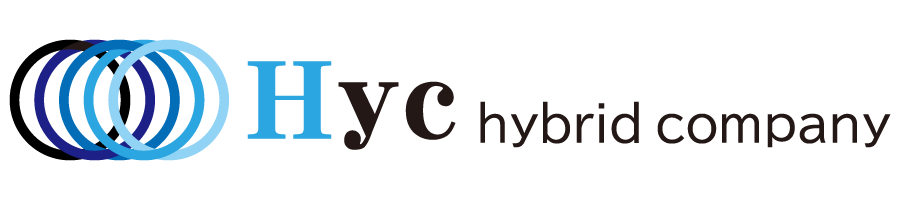脱炭素経営の成功事例10選|中小企業から大企業まで
脱炭素経営という言葉が注目されてから数年が経ちました。
大手企業はすでに再生可能エネルギーの導入やエネルギー効率の見直しを進め、
中小企業にもその波が広がりつつあります。
とはいえ、どこから始めればよいのか分からない、費用がどれほどかかるか想像できないといった声も多く聞かれます。
そこでこの記事では、脱炭素に取り組む企業の実際の事例を紹介しながら、
業界ごとの進み具合や、費用感、補助金の活用方法までを詳しく解説します。
経営判断としての脱炭素を、具体的にイメージできるヒントがきっと見つかるはずです。
脱炭素経営とは何か
「脱炭素経営」とは、事業活動における温室効果ガスの排出量を減らし、最終的にゼロに近づけることを目指す経営手法です。
この考え方は、2015年のパリ協定を契機に世界中で広まり、2020年以降は日本国内でも急速に注目されるようになりました。
政府は2050年までにカーボンニュートラル(実質排出ゼロ)を実現するという方針を打ち出し、
多くの企業に対しても排出削減だけでなく、経営全体を見直すよう求めています。
これは単なるCSRではなく、企業の競争力を高めるための投資とも言えるでしょう。
また、SDGsとの関わりも深く、特に「エネルギーの安定供給」「産業のイノベーション」「気候変動への対応」など、
複数の目標達成に直結する要素として、国内外の投資家や取引先からも注目されています。
脱炭素経営は一時的なトレンドではなく、長期的な経営判断の軸として定着し始めています。
すでに進んでいる業界とその特徴
脱炭素経営の取り組みは、すでに多くの業界で本格化しています。
特に、エネルギー消費量が大きく、環境負荷を減らすことで経済的なメリットが見えやすい業界では導入が進んでいます。
製造業(重工業・素材系)
鉄鋼、化学、セメントなど、エネルギーを大量に使う業種では、
CO₂排出量が多く、国や業界団体からも強い削減圧力を受けています。
そのため、再生可能エネルギーの導入や、製造プロセスの見直しが加速しています。
エネルギー業界(再エネ活用型)
電力会社やガス会社なども、再エネ事業へのシフトを急いでいます。
自社で発電設備を持ち、太陽光や風力の普及を促進している企業も多く見られます。
流通・小売業
イオンやセブン&アイなどの大手流通グループでは、店舗の屋根に太陽光パネルを設置し、
冷暖房や照明の電力をまかなうといった施策が実践されています。
物流センターではEVトラックの導入なども進んでいます。
特徴まとめ
- エネルギーコストの削減が即効性のあるメリットになる
- 技術革新によって投資回収が見込める分野
- 社会的要請が強く、企業ブランド向上にもつながる
遅れている業界とその背景
一方で、脱炭素経営の取り組みが十分に進んでいない業界もあります。
特に、構造的な課題を抱える業界や、初期投資に対する不安が大きい分野では、導入のスピードが遅れがちです。
飲食・サービス業
店舗数が多く、設備も小規模なケースが大半を占めるため、
個々の省エネ対策が分散しやすく、効果が見えにくい傾向があります。
加えて、人材不足や日々の業務に追われる現場では、長期的な設備投資の優先度が下がることも一因です。
建設業
現場ごとの個別対応が多く、統一的なエネルギー管理が難しい業界です。
また、資材の調達や重機の使用など、脱炭素化が難しい工程も多く残っています。
特徴まとめ
- 現場主導でエネルギー使用の全体最適が難しい
- 利益率が低く、初期投資に慎重な経営判断が多い
- 国の制度支援が十分に伝わっていないことも障壁の一つ
脱炭素経営の成功事例10選(業界別に紹介)
1. イオン株式会社(流通)
太陽光パネル導入、店舗単位での再エネ活用
2. 株式会社LIXIL(住宅設備)
製造拠点の省エネ化と排出量管理の徹底
3. トヨタ自動車(製造)
水素技術と再エネ導入でグローバルな対応
4. サントリーホールディングス(食品)
製造工程の排出可視化と削減目標の設定
5. 積水ハウス(建設)
ZEH住宅普及による家庭からの排出削減
6. ヤマト運輸(物流)
EV車導入と再エネ拠点の整備
7. 大和リース(中小建設)
現場単位での省エネ設計と再エネ化
8. 株式会社タイセイ(中小製造業)
補助金活用による太陽光設置とコスト削減
9. 株式会社アーバンエナジー(エネルギー)
地域との連携で地産地消のエネルギーモデル
10. 株式会社ミライ電機(サービス)
IoT活用でのエネルギー制御と社員意識向上
導入時のコスト感と補助金活用
主なコスト項目
- 再エネ設備(太陽光・蓄電池)
- 省エネ機器(LED、空調)
- 工事・診断費用
- EMSやIoTの導入コスト
中規模事業所の場合、300万〜1,000万円程度のケースが多い。
補助金活用で実質負担を3〜6割に抑えられる可能性あり。
主な補助金制度
| 補助金名 | 対象 | 補助率 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 省エネ投資促進(経産省) | 中小〜大企業 | 最大1/2 | 省エネ機器やEMSの導入支援 |
| 地域再エネ導入(環境省) | 自治体・企業 | 最大2/3 | 太陽光などの設置支援 |
| 自治体補助金 | 地域企業 | 1/3〜1/2 | 独自の再エネ支援策が豊富 |
成功例
タイセイ社:総額350万円 → 補助金200万円 → 実負担150万円
年間45万円の電気代削減、約3年で回収見込み
まとめ:脱炭素経営は「できるところから」でいい
企業にとって、脱炭素経営は避けられない時代になりました。
再生可能エネルギーの導入、省エネ機器の活用、補助金制度の活用など、取り組める手段は多岐にわたります。
すでに多くの企業が行動を起こし、経営上のメリットを得ています。
脱炭素経営のポイントまとめ
- 製造業や流通業など、導入が進んでいる業界がある
- 飲食業や建設業など、取り組みが遅れがちな業界もある
- 成功企業の事例から、実行可能な手法を学べる
- コスト面は補助金を活用することで大きく軽減できる
- 小さな取り組みでも積み重ねが将来の競争力につながる
脱炭素は義務ではなく、これからの企業価値を高める戦略です。
無理に完璧を目指す必要はありません。
まずは自社に合ったやり方で、できるところから始めてみましょう。
本件に関するお問い合わせ先
📩 contact@hybridcompany.co.jp
\この記事をシェアする/